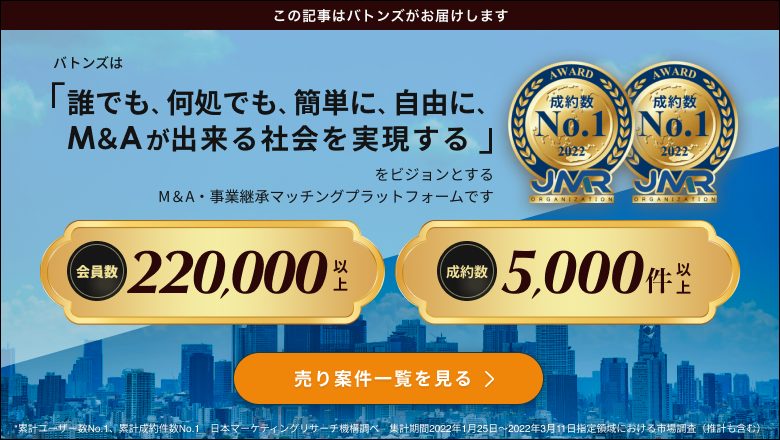「PMI」という単語は、M&Aについて調べたことがある方なら一度は目にしたことがあるでしょう。成功を左右する要素がいくつもあるM&Aですが、特に重要なのがPMIによる詳細な統合計画です。
この記事では、PMIの概要をはじめ、重要性や実行手順、注意すべき要素やポイントについて詳しく解説しています。実際の企業のPMI実行の事例も紹介していますので、M&Aを計画している方はぜひ参考にしてみてください。
PMIとは

PMI(Post-Merger Integration)は、企業の合併や買収が完了した後に行われる統合のプロセスです。ここでいう「統合」とは、具体的な業務内容や社内の意識・モチベーションも対象であり、経営方針だけを指しているわけではありません。
PMIにおける統合では、異なる企業同士の業務の合理化、また統合後の経営・業務の効率化やシナジーを最大化するための活動を行います。具体的にPMIで重要になる要素は、「組織文化の融合」「人事・人材の統合」「業務プロセスの再設計」「ITシステムの統合」です。
組織文化の融合
異なる組織の文化を調和させ、共通のビジョンを確立するために必要なコミュニケーションや、基盤となる互いの企業文化の共有が行われます。
人事・人材の統合
異なる企業間において、人事制度や評価基準の調整、人材戦略の統一、新たな業務形態・発足部署に対して適切な人材配置などを行います。
業務プロセスの再設計
異なる企業間において、統合後の業務の重複や冗長性を解消したり、効率化やツール等による自動化について検討・再設計を施します。
ITシステムの統合
それぞれの企業が保持するデータの一元化やシステムの連携が行われ、社内におけるITシステムを統合し、意思決定の迅速化や業務の円滑化を図ります。
これらのPMIの段階を適切に経ることにより、統合後の企業はより強固な基盤を築き、経済的成果や競争力の向上を実現することができます。
M&AにおけるPMIの重要性や役割

PMIを準備し、適切に行うことでM&Aの成功確率は上がります。しかし、PMIをしっかりと行えている企業は少ないです。
理由としては、譲渡企業(売り手)から統合の合意を引き出すことに注力してしまい、統合後のプロセスであるPMIを後回しにしがちなことが挙げられます。統合の合意形成はもちろん大切ですが、それ以上に統合後のプランこそ経営において重要な課題になります。
M&Aにおいて、PMIに期待できる効果には以下の3つが挙げられます。
⚫︎統合後、譲渡企業(売り手) と譲受企業(買い手) それぞれの社員において、トラブルや離職といった問題を防げる
⚫︎業務や事業、オペレーションやITシステム上の相違点において、不具合や失敗のリスクを小さくできる
⚫︎企業統合後のシナジー効果を活かし、より安定した生産性の高い経営を実現しやすい
これらの効果は、M&Aを成功させるためには欠かせない要素です。では、PMIを上手く実行するためには、どのような手順を踏めば良いのでしょうか。ここでは、PMI実行の流れについて見ていきましょう。
①M&Aの方針策定
PMIに大きく影響を与えるのが、M&Aにおける方針、つまり統合形式の選択です。統合形式は大きく分けて3つあり、各形式の特性を理解した上で統合形式を選ばなければなりません。
統合形式の選択は、PMIに影響を与える可能性があります。それぞれの特徴を理解したうえで、統合の基本方針を策定することが重要です。
| 統合形式 | 特徴 |
|---|---|
| 連邦型統合 | 譲渡企業(売り手)を子会社として存続させ、経営の自律性を尊重する方針。譲渡企業のこれまでの企業文化を維持し、経営方針も保持されるため、社員の反発は少ない傾向にあることも特徴。ただし、PMIが思うように進展せず、M&Aの効果を十分に発揮できない可能性もある。 |
| 支配型統合 | 譲渡企業(売り手)を子会社として存続させながら、積極的に経営に関与していく方針。経営方針や事業戦略が大きく見直されるなど、譲受企業(買い手)の意向が強く反映されるケースが多くなる。関与に関して支配色が濃すぎると社員の反発を招くため、バランスを取りながら慎重に話を進める必要がある。 |
| 吸収型統合 | 「吸収合併」「吸収分割」「事業譲渡」などの手法を通じ、譲受企業(買い手)が譲渡企業(売り手)の組織や事業を一体化して統合する方針。譲受企業の意向が反映されやすく、統合プロセスは迅速だが、適切な進め方を行わないと現場の負担を大きくしてしまう可能性がある。 |
「吸収型統合」については、「吸収合併」「吸収分割」「事業譲渡」の3つの手法があり、それぞれの手法の内容は以下になります。
吸収合併:譲渡企業(売り手)の法人格を廃止し、譲受企業(買い手)がその権利や義務を引き継ぐ手法
吸収分割:譲渡企業が行っている事業の一部または全体の権利や義務を分割し、譲受企業に引き継がせる手法
事業譲渡:譲渡企業が行っている事業の一部または全体を譲受企業に売却する手法
統合する際には、経営方針や事業計画、各現場の業務の人材配置や再設計なども重要です。また、個人差はあるものの社員は不安を感じているため、社員の感情についてフォローすることも大切です。
②統合計画の策定
M&Aの方針策定の後は、PMIをどのように行うのか統合計画について策定します。クロージング(M&Aにおいて経営権の移転を完了させる最終手続き)が完了した後、次のステップとして3〜6ヶ月の間に実施する作業を洗い出します。
その際、まずは被買収企業の資産、競争力、市場状況、内部ルール、社員の反応などを考慮し、PMIの手法や手順、全体のスケジュールを定めます。この段階で統合効果のシナジーを引き出し、期待する買収効果を発揮できるかどうかが決まるため、慎重に策定を行わなければなりません。
これらの策定には、組織再編に関する人事労務や内部ルールの見直し、事業再編に関する設備投資やサプライチェーンの再構築といった作業も含まれます。後述するデューデリジェンスの結果を踏まえて優先順位を決定し、具体的に実行していきます。
これらの策定・作業に対し、譲渡企業(売り手)譲受企業(買い手)それぞれが必要な対処を計画に含めて実行することで、統合プロセスの円滑化や買収による業績向上の結果を得ることができます。
③100日プランの作成
100日プランは、M&A成立後から100日(3ヶ月)の間に実行される計画です。この計画では主に、PMIにおいて特に優先度の高い課題に必要な作業に着手するため、いつ誰がどんな手順で進めるかをスケジュール化しておかなければなりません。
100日プランを作成する理由は、企業のあるべき理想の姿を想定し、その実現に向けて必要な変化を促進させるためです。企業の現状と理想の姿の間にあるギャップを100日プランによって特定し、各課題・修正点において、具体的な解決策を導き出して埋める作業を行います。
そのため、まずは挨拶や個別の面談など、優先順位の高い課題を100日プランとしてスケジュール設定し実行します。提携先やパートナーとなる社員・関係各所との関係構築に重点を置き、この段階で統合後の企業内の足場を固めておくことが大切です。
M&Aの成立後は、実際に統合した企業が経営として成長を始めるには1~2年かかります。特に最初の100日は重要であり、人材配置や業務プロセスの再設計はもちろん、同時に長期的な活動を支える体制づくりが必須になるでしょう。
100日プランは基本的に、M&Aのクロージングまでに策定し、クロージング後には計画に基づいて迅速にアクションを起こすのが定石です。また、多くの場合PMIの専任担当者はおらず、社員が通常業務に加えてPMI業務を行うことも押さえておく必要があります。
状況によっては複数のプランが同時進行する場合もあり、プロジェクト間で連携する必要があるかもしれません。そのような場合には、PMO(Project Management Office)を設置し、個々のプロジェクトをマネジメント支援しながら100日プランを進めると良いでしょう。
④M&Aの実行
100日プランの計画を作成した後は、M&Aの最初のフェーズとして実行に移します。前項でお伝えした通り、まずは関係各所への挨拶や個別の面談など、これから新体制で経営を推進するにあたっての足場を固めることからスタートします。
100日プランの実行後は、100日プランに収めることのできなかった施策について実行計画として策定します。具体的な取り組みをあぶり出すため、統合計画の策定の段階で、譲渡企業(売り手)の経営課題や売上拡大など、コストシナジーに必要な要素を洗い出しておくことが重要です。
また、PMIはプロジェクトによって対応すべき課題や優先順位が異なる上で、長期的な取り組みになるため、担当者のモチベーションを高く保つ工夫が必要になります。各社のPMI担当者に対してM&Aの目的や意義を何度も伝え、当事者意識を持ってPMIの取り組みに邁進する状態を作る、といったアプローチも必要になるでしょう。
⑤モニタリング
M&Aの実行においては、実行計画の進捗状況をモニタリングする必要があります。PMI担当者や現場で働く各社の社員のモチベーションや関係性についてチェックし、必要な場合は対応策を講じるようにします。
また同時に、統合計画策定時の項目を実現するため、分科会の報告を基に進捗状況を確認し、必要に応じて改善策を策定しましょう。各分科会ごとに対応策を検討・実施し、譲渡企業(売り手)の価値向上や業務の円滑な遂行を図ります。領域によっては、KPIを設定して定量的に施策の成果を評価する必要もあります。
さらに、M&A実行後1年など節目では、両者の統合状況や事業や施策の取り組みの進歩状況を振り返ることも重要です。統合した企業の将来の成長に向けた方針や、遂行中の実行計画の改善を行うことも大切になるでしょう。
PMIを成功に導くポイント

PMI自体の準備を適切に行ったからといって、PMIの実行が上手く行くとは限りません。PMIを成功させるためには、押さえておくべきポイントがあります。ここでは、PMIを成功に導く5つのポイントについて見ていきます。
PMIマスタープランの作成
M&Aに限らず、何事も骨組みとなる計画がなければ方向性が定まらず、統合の効果を得ることなどできなくなってしまいます。統合後の業務開始日までには、PMIのマスタープランを必ず作成しておきましょう。
なお、マスタープランには戦略やマネジメント、人事体制や業務プロセスといったものを盛り込みます。
適切な人材の選定
PMIによる統合を円滑に進めるには、部門を横断して連携することが重要です。そのためには、専任のPMI担当者が求められ、統合を指揮する責任者を任命することがPMIの一環です。
特に統合後の経営に重要な子会社には、すぐに専任PMI担当者を現場に派遣し、譲渡企業(売り手)側の社員と現場で協力し合いながら、密な協議を行うことが不可欠です。
また、買収された譲渡企業ではモチベーションの低下が起こっている場合があります。そうした状況においてPMIを円滑に進めるためには、譲渡企業(売り手)譲受企業(買い手)双方の企業で、PMIを主導する人材を適切に選択しなければなりません。
統合によって新たに作られた部署においても、適材適所の人材配置は重要です。特に中小企業では、組織の西武が不十分であり、各部署には人員が偏って配置されているケースが多く見られます。
従って統合後の人員整理の際には、まずは組織全体の人員配置の見直す必要があり、取り分け部署やセクションごとに再確認し、適切な組織体制が構築されているか再評価する必要があるでしょう。
デューデリジェンスによる調査
デューデリジェンスとは、M&Aの対象企業に対して詳細な調査を行う活動を指します。十分なデューデリジェンスを行うことで、統合に必要な情報が収集でき、PMIを順調に行うことができます。
デューデリジェンスでは基本的に、経営体制や事業規模といった、譲渡企業(売り手)の全体構造を把握する調査が求められます。しかし、全体構造だけでは不十分であり、より踏み込んだ部分にも着目しなければなりません。
例えば、人事部や法務部などの制度面といった部署ごとの調査です。細かな社内文化・方法論について調べ、統合後に障害にならないように予防しておく必要があるでしょう。PMIの効果を最大限引き出すには、デューデリジェンスに必要なリソースを投下することが重要です。
また、外部の調査会社等の専門家に依頼し、適性な買収価格の判断のための材料を集めることも必要です。譲渡企業からの情報や譲受企業(買い手)による調査だけでは十分とは言えず、客観性や信頼性に欠けている場合もあるからです。
例えば、財務・法務・労務において思わぬリスクが隠れていたり、譲渡企業側が把握できてない自社のリスクを抱えているケースもあるでしょう。そういった、顕在化していないリスクについても第三者の介入を得て十分に調査し、M&Aを進めなければなりません。
経営ビジョンの共有とリーダーシップ
社内に向けて突然M&Aを発表した場合、「これからどうなるのか?」と社員は強い不安を抱いてしまいます。そのため、M&Aの推進は、社員に対して説明しながら行う必要があります。経営陣は社員に対して、M&Aに至るまでの経緯や事情をしっかりと説明をし、迅速に合意形成を得る必要があるでしょう。
ただし、社員と一言で表しても、役職によって立場が異なる点も留意しなければなりません。M&Aを伝える際には、役職ごとに説明のタイミングを区別することが重要です。経営や事業全体に深く関わる役職者から先に説明するほうが良いでしょう。
特に、先に伝えるべきなのは、経営に大きく関わっている役員陣といった上層部です。説明不足は、社員との信頼関係を大きく損ねる要因なので、経営を支えてくれる役員陣との関係悪化や離職を防ぐ意味でも、真っ先に伝えなければなりません。
その後、各部署の部長やリーダークラスへの伝達、社員への伝達と段階を経て、M&Aが行われることを社内に浸透させ理解を促します。
社内への説明を適切に行えていない場合、M&Aの交渉に悪影響が出たり、譲渡企業(売り手)側や各方面に多大な迷惑をかける可能性もあるため注意が必要です。そのためには、経営陣のリーダーシップがカギとなります。
オペレーションやシステムの統合
PMIを推進する際に特に難しい課題となるのが、業務のオペレーションやITシステムの統合です。統合前の実務担当者は、業務効率化による仕事の減少や、業務フロー変更によるミスの増加や時間がかかってしまうことに懸念を抱く場合が多いからです。
とはいえ、オペレーションやITシステムの統合を避けるわけにはいかないのが現実です。オペレーションやITシステムの統合をしないまま業務を進めることは非効率であり、引いては生産性への悪影響にも繋がって、経営そのものに打撃を与えることになりかねません。
従って、以下の要点を押さえながら慎重にオペレーションやITシステムの統合を進めることが求められます。
【社員へのヒアリング】
現場の実務担当者の役割、業務フロー、システムの利用法などを把握した上で、その業務フローが採用されている理由をヒアリングによって深掘りします。譲渡企業(売り手)の強み・弱点を理解するためにも大切です。
【実務担当者の心をサポートする】
これまでのオペレーションやITシステムに慣れ親しんだ社員にとって、やり方を刷新することは心理的に負担となります。M&Aの意義や重要性を説明するだけでなく、社員の抱く不安や複雑な気持ちについても寄り添い、配慮しながら統合を進めなければなりません。
【理想的な設計】
オペレーションとITシステムの統合後の理想的な状態をイメージしておくことも重要です。目の前の業務を効率化するだけでなく、企業としての成長に適した形のオペレーションやITシステムを再設計することが望ましいと言えるでしょう。
PMIの事例
PMIの手順とポイントをお伝えしたところで、実際の企業がM&Aを推進する際のPMIの実行のやり方について見ていきましょう。PMIの方針により、M&Aが上手く行ったケースと上手く行かなかったケースが存在します。
ここでは、サントリーホールディングス(株)とウォルマートの事例を参考にします。
事例➀
サントリーホールディングス(株)は、2014年に米国のウィスキーメーカーであるビーム社(現ビームサントリー)を総額160億ドル(日本円で約1兆6500億円)で買収しました。
この買収により、サントリーはスピリッツ(蒸留酒)事業を展開し、米国を含む世界各地でジムビームやメーカーズマークなどのバーボンウィスキーを販売しています。その結果、売上高は43億ドルを超え、サントリー社は世界の高級スピリッツ市場において第3位にまで成長しています。
また、サントリーは買収後もビーム社の伝統を尊重し、ビーム社の2つの現地蒸留所を維持するPMIの方針を採用しています。この戦略は功を奏し、買収後の2015年12月期の決算において、ビームサントリー社は前年同期比123%の売上成長を果たしました。
サントリーのM&A戦略は事業の成功と拡大のみならず、企業文化や伝統の調和を重視するPMIで成功した、貴重なモデルケースだと言えるでしょう。
事例②
米国の大手スーパーマーケット、ウォルマートによる西友の買収は、PMIに失敗したことによって上手く行かなかった例です。
ウォルマートは2009年に行った西友の買収後、低価格帯の人気商品を取り揃える戦略を取りましたが、思うような成果を上げることができませんでした。その結果、2020年にウォルマートは西友の持株比率の引き下げを発表しています。
ウォルマートは10年以上保有していた西友の株式の85%を売却し、そのうち65%を米国投資ファンドのKKR(コールバーグ・クラビス・ロバーツ)に、20%を楽天に譲り渡しています。可能な限り多くの投資回収を達成するため、残り15%の株式のみ保有する形を取りました。
ウォルマートの例のように、PMIの戦略が上手く行かず、成果が上がらない場合は取引が中止されるケースもあります。M&Aの中止・解消は、消費者やユーザーからの離反を生んでしまう可能性もあるため、リスクとして考慮しなければなりません。
その他にも、企業同士の統合後の新体制に反発する社員が離職したり、組織文化やオペレーションなどの統合が上手く行かず、組織全体のモチベーションが低下してしまうことも、PMIの失敗の例として挙げられるでしょう。
まとめ
M&Aでしっかりとシナジー効果を発揮するには、いかに計画性のあるPMIを策定し、適切に実行できるかです。企業が統合した後のPMIが上手くいかなかったことで、これまで自社を支えてくれた大切な消費者やユーザーが離れてしまう可能性もあります。
M&Aを検討している経営者は、まずは対象とする企業の良い部分とリスクを把握した上で、PMIの戦略を練っていきましょう。PMIこそがM&A後の会社の経営・事業推進を左右することになります。
M&Aを仲介する「バトンズ」では、事業承継や企業の売買などさまざまなM&A案件のマッチングを行っています。中小規模の案件も多いため、今後の事業展開に選択肢が広がるでしょう。また、手数料についても一般的なM&A仲介業者やマッチングサービスと比較すると安価に抑えることが可能です。
PMIについても、これまでのM&A仲介の経験から適切なアドバイス・サポートが可能です。企業をさらに発展させていこうとする際には、バトンズでM&Aを検討してみてはいかがでしょうか。
こんなお悩みありませんか?
つなぐマッチングプラットフォームです。
累計5,000件以上の売買を成立させています。
またM&Aを進めるためのノウハウ共有や
マッチングのための様々なサポートを
行わせていただいておりますので、
まずはお気軽にご相談ください。
編集部ピックアップ
- M&Aとは?流れや注意点、スキームなどを専門家がわかりやすく解説
- 事業譲渡とは?メリット・手続き・税金などについて専門家が解説
- 中小M&Aガイドラインとは? 概要や目的を詳しく解説
- 企業買収とは?M&Aとの違いは何?メリットや手続きの流れをわかりやすく解説
- 会社売却とは?M&Aのポイントや成功事例、IPOとの違いも解説
- 【完全攻略】事業承継とは?
- スモールM&AとマイクロM&Aとは?両者の違いとメリット・デメリットを解説
- 合併とは?会社合併の種類やメリットデメリット・手続きの流れ・必要書類を解説
- 後継者のいない会社を買うことで得られる多くの利点とは?
- カフェって実際のところ儲かるの?カフェ経営の魅力と開業方法
その他のオススメ記事
-

2024年12月11日
人の命を守るバックミラーの製造。父から受け継いだ誇りある仕事を、熱意ある会社へ事業承継
大阪府を拠点にアルミミラーを中心とした製造・加工業を営む「株式会社尾崎鏡工業所」は、2024年9月、愛知県でガラス製品の製造加工等を手掛ける「...

-

2024年09月17日
トラック・運送業のM&A動向 | メリットや事例について解説【2024年版】
運送業界は、 M&Aの需要が高まっている業界のひとつです。その背景には、後継者不足や2024年問題などさまざまな理由があり、事業規模の大小問...
-

2024年09月05日
未来への想いを共有できる会社とM&Aで手を組みたい。バディネットは、すべてのモノが繋がる社会を支えるインフラパートナーへ
2012年に電気・電気通信工事業界で通信建設TECH企業として創業したバディネット。2024年現在、5社の買収に成功して業容を拡大させています。今回は...