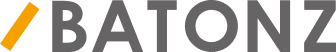調剤薬局・化学・医薬品のM&Aなら
案件数・成約数No.1の
バトンズ
案件数・成約数No.1の
バトンズ



※M&Aプラットフォーム市場における累計成約件数・総登録案件数・成約件数2021~2023年度(見込値を含む)No.1
出典:デロイト トーマツ ミック経済研究所 2023年発刊「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2023年版】」 (mic-r.co.jp)
出典:デロイト トーマツ ミック経済研究所 2023年発刊「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2023年版】」 (mic-r.co.jp)
調剤薬局・化学・医薬品のM&A案件一覧
業種で絞り込む
地域で絞り込む
北海道 (13)
|
東北地方 (39)
|
関東地方 (478)
|
甲信越・北陸地方 (35)
|
東海地方 (78)
|
関西地方 (180)
|
中国地方 (28)
|
四国地方 (15)
|
九州・沖縄地方 (60)
|
海外 (29)
調剤薬局・化学・医薬品のM&Aでチェックすべきポイント
調剤薬局・化学・医薬品業界の特徴
調剤薬局・ドラッグストアは、現在約5万8千もの店舗があり、大手による中小店舗のM&Aが増加しています。調剤薬局は、国のバックアップによる医薬分業で市場拡大してきたこともあり、医師の処方箋に従って調剤することを業としています。立地はほとんどが医療機関の門前となっています。一方で、国は医療費削減のために、外来患者を減らす方向です。今後、中長期的な視点にたつと、大病院の門前という優位性は徐々に失われ、地域医療の担い手として患者に向き合う姿勢が生き残りのための必要条件になってくると思われます。
調剤薬局・ドラッグストア
店舗売上の安定性は、立地に依存する部分が大きく、近隣医療機関がどの程度患者を抱えているのかを確認することが重要です。大病院の門前に構えようとする競合店も多数存在するため、医療機関との距離だけでなく、患者の通院動線など、詳細な分析が必要となります。また、近隣医療機関の移転、近隣診療所の事業承継問題による廃業等は大きな経営リスクとなるため、店舗立地を評価・検討する際は、現状だけでなく将来の見通しも確認しておきましょう。収益は技術報酬と薬剤料に分かれ、薬剤の販売価格は国によって決められていますが、仕入価格は事業者によって異なるので、薬剤料と仕入価格の差(薬価差益)がどの程度取れているかがその事業者の利益水準に大きく影 響します。買収対象の薬価差益の水準が現状はどの程度かを把握しておきましょう。人材の面では、大手チェーンの出店攻勢等を背景に、近年薬剤師不足が深刻となっています。薬剤師のシフトを見るとパート薬剤師が数名でまわしている状況であったり、M&Aに伴い退任予定のオーナー夫婦がフル稼働で運営しているような状況も多く見られます。M&A後に現在の人員体制で運営を行っていけるかをきちんと確認しましょう。M&Aの譲渡価格について、中小企業の株式価値は時価純資産に利益2~5年程度の営業権(のれん代)を加味した金額となることが多いですが、調剤薬局業界においてはEBITDA(営業利益+減価償却費)の4倍程度が1つの目安となっています。この目安をもとに、M&A後に必要となる改修費用や設備投資、近隣医療機関との関係の継続性などを勘案して調整・決定していくことになります。
医薬品製造・卸売
医薬品卸売業の営業担当者は、医薬品卸販売担当者「MS(マーケティングスペシャリスト)」と呼ばれており、多数の製薬メーカーの商品を比較・提案し、医薬品や医療材料、医療機器等を医療機関に販売しています。医薬品製造業の営業担当者は、医薬情報担当者「MR(メディカルレプレゼンタティブ)」と呼ばれており、他社製品対比での自社製品優位性を含め、医薬品に関する情報を医師や薬剤師などの医療従事者に提供しています。MRは価格交渉を含めた販売自体は行わず、MSが販売をしています。昨今はネットメディアによる情報提供も進んでおり、MS・MRの体制について確認しておきましょう。また、医薬品製造業では、薬価の引き下げと研究開発費の増大により、経営環境は厳しさを増してきています。特に、研究開発費については、新薬開発競争のために相当規模の資金を投入しており、巨額の投資に耐えうる財務基盤が必須となっています。
化学品製造・卸売
化学品製造・卸売業のM&Aを進めるに当たり重要なのは、特権侵害の有無確認です。本業界には、レシピ、製法など秘中の秘が存在していますので、他社の特許を侵害していないか等に関する十分な調査と確認が必要です。また高収益企業が多いことから、財務内容はあまり心配が無い一方で、使用する薬品によっては土壌汚染、大気汚染、労働問題等の心配がありますので、それらについても十分な調査と確認が必要になります。
化粧品企画・製造
化粧品製造業は、完成品の製造業者でなくても「化粧品製造業許可」が必要となり、包装表示で販売元になる場合は「化粧品製造・販売業許可」も必要となります。半製品のみを出荷する事業者やOEM生産のみの事業者はこの許可は不要となります。化粧品の広告手法はテレビCMからSNSや動画サイトへと移ってきており、ネットを活用したマーケティング戦略が求められています。特に、SNSにおける口コミの影響力は非常に大きく、Instagramなどで化粧品メーカーから直接購入することも可能になった現在、SNSを活用したマーケティングの実施状況や今後の活用可能性は検討する必要があります。海外ブランドは、基礎化粧品からファンデーションなどのメークアップ商品まで、男性用の商品ライナップを増やしています。中小企業にとってはハードルも高くなりますが、性別を超えて顧客を拡大することができれば国内需要拡大の可能性もあるため、検討してみる価値のあるテーマと言えます。
サプリメント・健康食品
サプリメント・健康食品業界は、薬事法が規定する製品群と隣接しているため、パッケージや広告宣伝の文言等が薬事法に抵触していないか細部に渡る注意を払う必要があります。また、原材料の適法性においても契約、ビジネス周りの確認を十分に行ってから案件を進めましょう。加えて、過去から現在に至るまでの係争の有無も確認してください。
工業用繊維
工業用繊維事業のM&Aを進めるあたり必要不可欠なのは、通常の財務や法務的な検証はもちろんのこと、何より技術面での検証です。なぜなら、当該製品が現在主流であったとしても新素材の開発によって陳腐化する可能性もありますし、最終製品やどのようなものに利用されているかによっても、その将来性は大きく変わるからです。従って、当該企業が製造している工業用繊維について、それらの観点を踏まえてきちんと検証する必要があります。
理化学機器
理化学機器業界は技術面での優位性が非常に重要な業界であるため、研究開発及び製造工程で古参社員が中心となっている場合は、後継者が育っているかという観点にも充分注意を払う必要があります。また、特定の取引先に依存しているケースも散見されるため、当該企業の動向についても調査、確認する必要があります。