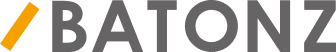調剤薬局・化学・医薬品のM&Aなら
案件数・成約数No.1の
バトンズ
案件数・成約数No.1の
バトンズ



※M&Aプラットフォーム市場における累計成約件数・総登録案件数・成約件数2021~2023年度(見込値を含む)No.1
出典:デロイト トーマツ ミック経済研究所 2023年発刊「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2023年版】」 (mic-r.co.jp)
出典:デロイト トーマツ ミック経済研究所 2023年発刊「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2023年版】」 (mic-r.co.jp)
調剤薬局・ドラッグストアのM&A案件一覧
業種で絞り込む
地域で絞り込む
北海道 (6)
|
東北地方 (34)
|
関東地方 (238)
|
甲信越・北陸地方 (19)
|
東海地方 (50)
|
関西地方 (115)
|
中国地方 (21)
|
四国地方 (10)
|
九州・沖縄地方 (32)
|
海外 (2)
調剤薬局・ドラッグストアのM&Aでチェックすべきポイント
調剤薬局・ドラッグストア業界の特徴
調剤薬局・ドラッグストアは、現在約5万8千もの店舗があり、大手による中小店舗のM&Aが増加傾向にあります。調剤薬局は、国のバックアップによる医薬分業で市場拡大してきたこともあり、医師の処方箋に従って調剤することを業としています。立地はほとんどが医療機関の門前となっています。一方で、国は医療費削減のために、外来患者を減らす方向です。今後、中長期的な視点にたつと、大病院の門前という優位性は徐々に失われ、地域医療の担い手として患者に向き合う姿勢が薬局生き残りのための必要条件になってくると思われます。
立地と近隣医療機関
調剤薬局店舗の売上は、その立地に依存する部分が大きくなります。大病院の門前にお店を構えていれば、安定的な集客が見込めます。したがって、近隣にある医療機関がどの程度患者を抱えているのかが店舗収益の安定性をみる上で重要となってきます。大病院であればあるほど、門前に構えようとする競合店舗も多く存在することが想定されますので、医療機関との距離だけでなく、患者が通院する動線を勘案する等、より詳細な分析が必要となります。また、依存している近隣医療機関の移転や、近隣診療所の医師の事業承継問題による廃業は大きな経営リスクとなります。したがって、店舗立地を評価・検討する上では、現状だけでなく将来の見通しも確認する必要があります。
薬価差益
調剤薬局は、医療機関から発行された処方箋に従って、薬剤を患者に提供することで利益を得ています。この提供するサービスや薬剤の販売価格は国によって決められており、技術報酬と薬剤料に大別されます。このうち、薬剤料に関しては、仕入価格が事業者によって異なりますので、薬剤料と仕入価格の差(薬価差益)がどの程度取れているかがその事業者の利益水準に大きく影 響します。大手チェーンであれば、バイイングパワーにより仕入価格を抑えることができるので、一般的には中小の調剤薬局事業者よりも薬価差益は大きく取れています。したがって、買収対象の薬価差益の水準が現状はどの程度かを把握することにより、M&A後にどの程度利益改善の余地があるのかを推定することができます。
薬剤師の数
大手チェーンの出店攻勢により店舗数が拡大していること等を背景に、近年薬剤師不足は深刻となってきています。現に問題なく運営されている調剤薬局であっても、薬剤師のシフトを見てみるとパート薬剤師が数名で回している不安定な状況であったり、M&Aに伴い退任予定のオーナー夫婦がフル稼働してなんとか運営しているような状況は多く見受けられます。したがって、M&A後に現在の人員体制で運営を行っていくことができるのかどうかを確認することが重要となります。
譲渡価格の考え方
調剤薬局業界のM&Aの譲渡価格は、一般的な中小企業の価格調整とは異なる算定方式が用いられることがあります。一般的に中小企業の株式価値は、時価純資産に利益2~5年程度の営業権(のれん代)を加味した金額となることが多くなりますが、調剤薬局業界においてはEBITDA(営業利益+減価償却費)の4倍程度が1つの目安となっています。この目安から、引継ぎ後に必要となる改修費用や設備投資、あるいは近隣医療機関との関係の継続見込みなどを勘案して調整・決定していくこととなります。