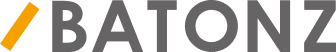医療・介護のM&Aなら
案件数・成約数No.1の
バトンズ
案件数・成約数No.1の
バトンズ



※M&Aプラットフォーム市場における累計成約件数・総登録案件数・成約件数2021~2023年度(見込値を含む)No.1
出典:デロイト トーマツ ミック経済研究所 2023年発刊「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2023年版】」 (mic-r.co.jp)
出典:デロイト トーマツ ミック経済研究所 2023年発刊「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2023年版】」 (mic-r.co.jp)
医療・介護のM&A案件一覧
業種で絞り込む
地域で絞り込む
北海道 (116)
|
東北地方 (172)
|
関東地方 (1458)
|
甲信越・北陸地方 (151)
|
東海地方 (352)
|
関西地方 (713)
|
中国地方 (161)
|
四国地方 (52)
|
九州・沖縄地方 (336)
|
海外 (18)
医療・介護のM&Aでチェックすべきポイント
医療・介護業界の特徴
医療業界は、高齢化に伴う医療ニーズが増える中、医療費の抑制も進められ、経営状況が苦しい医療機関が多く、病院の4割が赤字と言われています。患者に対する医師や看護師が不足しており、医療従事者の人材不足も深刻です。M&Aでは、院長の高齢化により、クリニックを個人開業医が買収する事例も増えてきています。介護業界は、介護保険の財源も厳しい状況の中、介護施設や介護職員の人材不足が課題となっています。一方で、必然的にサービス需要が高まっていくため、異業種からの参入等、M&Aでは注目の業界となっています。
クリニック
従業員との雇用契約は原則として引き継がないため、もし従業員を継続して雇用したい場合には、新院長と新たに雇用契約を交わすことになります。引き継ぎ前に前院長ときちんと相談の上、検討しておきましょう。クリニックのM&Aは、医療機器等の資産を引き継げることに加え、カルテ情報を引き継げることが最大のメリットとなります。開業後の早期黒字化に大きく貢献するものとなります。一方でカルテ情報は個人情報に該当するため、個人情報保護法の適用を受けますが、医院継承におけるカルテ情報の引き継ぎについては第三者提供に該当しないという適用除外項目が該当します。ただし、カルテ情報を引き継いだ医師が、診療等の医療行為をする目的の範囲を超えて個人情報を使った場合は個人情報保護法に抵触するため留意しておきましょう。クリニックM&Aの譲渡価格は、「引き継ぎ対象資産の時価」+「営業権(のれん代)」がベースの考え方となります。一方で、カルテ情報が無形資産ののれん代として譲渡価格に上乗せされることもあります。引き継ぐ資産の時価情報、カルテ情報の評価方法について事前に情報収集、調整しておきましょう。
病院
医療法改正で、出資持分の定めのある医療法人を設立できなくなりましたが、現状も医療法人の約8割が出資持分ありの医療法人です。医療法人のM&Aでは、出資持分の定めのある社団法人であるケースが多く、出資者に財産権が認められる経過措置型医療法人と、持分の払戻等は払込出資額を限度とする出資額限度法人があるため確認が必要です。医療法人の場合、「社員総会」が意思決定機関、「理事会」が職務執行機関という位置付けであり、出資持分と意思決定について重要な調整ポイントとなります。診療報酬の観点では、レセプト枚数により規模感を確認し、支払基金からの入金通知書を入手し、手続が適正に行われているか、過誤請求が生じていないか等の確認も必要です。建物や医療機器の老朽化が進んでいる場合、引継ぎ後に多額の修繕投資が必要になるため、税務上の時価による評価では難しいケースもあります。医療機関の土地は流動性が低く、相続税評価等の一般的に採用される評価とは連動しないこともあります。エンジニアリングレポート等を活用し、適正な時価や中長期的に必要な修繕費用などを把握しておきましょう。人材面では、採用ルートの有無により経営の安定性を予測できるため、医大の医局や地元看護専門学校など、一定のルートを確保しているかを確認しましょう。また、MS法人を積極的に活用している医療法人の場合、正常収益力の把握ならびにM&A後のMS法人の取扱いを検討する必要があり、MS法人を含めた対象医療法人グループのビジネスフローを分析しましょう。株式会社をはじめとする事業会社のM&Aとは異なり、出資持分の有無、医療法・各自治体の許認可といった業界特有の事項に考慮してM&Aを進める必要があります。「持分の定めのある法人」「持分の定めのない法人」のどちらかによって、取り得るM&Aの手法も異なるため留意しましょう。
医療機器
医療業界のM&Aを進める上で重要なのは、やはり許認可関連です。基準をきちんと満たしているかといった財務面だけではなく、コンプライアンス面でのチェックも十分に行ってください。また、開発に要する費用も多額で財務的に厳しい企業も存在していますので、開発費や在庫等の資産性があるのか、チェックする必要があります。
デイサービス・ショートステイ
介護保険制度があるため、地域で若干の差があるものの、9割を市区町村、1割が利用者負担となります。売掛金回収のリスクは低いですが、通所者・入所者数の推移と資金繰りは確認しておきましょう。人材の面では、介護業界は賃金水準が総じて低く、労働環境も厳しいため、好況期の売り手市場では人材確保が難しくなります。また、事業者間の有資格者の人材獲得競争も激しいため、苦労して採用できても早期に転職してしまうといった離職率が高い問題を抱えている事業者が多くなります。さらに、人手不足を背景に、募集・採用コストの増、派遣社員のコスト増といった人件費負担が大きくなるのに加え、十分な人員が確保できないことで利用者数を絞らざるを得ない悪循環になっている事業者も一定存在しています。人員体制と人員の定着率をしっかり把握しましょう。 介護施設の稼働率は「年間延べ利用者数」÷「年間延べ定員数」で計算され、稼働率90%超が優良施設と言われています。稼働率の経年・月次での水準をを確認しましょう。また、施設規模に応じて人員基準や設備基準があり、生活相談員・看護師・介護職員等の常勤人数に指定があり、利用定員・居室・食堂等に関しても定めがあります。基準を満たして施設運営がされていることの確認が重要になります。
老人ホーム
これは介護事業全般に言えることですが、許認可、介護報酬など公的セクターとの関わりが非常に多いため、コンプライアンスについては十分に配慮する必要があります。また商談を進める上で、許認可権限を持つ都道府県との相談や打ち合わせは必須ですので、彼らとの関係性も確認しつつ配慮を忘れないようにしてください。加えて、介護報酬の変更に伴う業績変動にも注意が必要です。これらは、数年に1度改定されます。そして、基本的に本事業は設備産業であり初期投資額が大きく膨らんでいるケースが多いため、借入で賄っている場合には、その返済負担が重くなっているケースも散見されますので併せて注意が必要です。
グループホーム
グループホーム事業は、基本的に施設産業であるため、初期投資を借り入れで賄っている場合はその返済負担が重い企業、或いは定員いっぱいで運営しているのにも拘らず赤字体質が常態化している事業所等、何らかの対策が必要になっている事業者が多いのが事実です。また、数年に1度改定される介護報酬の変更に業績が大きく変動する場合がありますので、これらの影響を加味したうえで、余裕を持って資金繰りを行うことが非常に重要となります。
訪問系サービス
訪問系サービス業には、許認可及び公的扶助の受給という特徴があるため、コンプライアンス体制及び不正受給の可能性がないかを重点的に確認する必要があります。また、多数の労働者を雇用しなければならない業種でもあるため、労働時間や未払い賃金など労務関連の問題が存在していないか、しっかりチェックしてください。
障害児・障害者支援事業
障害児・障害者支援事業の店舗や事業所などは賃貸で運営している場合が多いので、その契約にチェンジオブコントロール条項(株主などが変わった場合貸主の許認が必要)がないか、承諾を得られるかどうかをチェックしてください。また、他と同様に許認可業種であることに加え、補助金や助成金とも密接に関わっていますので、受給に足る基準が守られているか、不正受給などに関与していないか、細かく確認することが非常に重要です。
福祉用具レンタル、販売、住宅改修
当事業で特徴的なのは、取り扱う用品の評価について売り手と買い手で意見が割れることです。レンタル事業が最も顕著で、売り手としてはまだまだ使えるのだから価値を見てほしいと言う思いが強く、一方で買い手は償却が終わっているので価値はゼロであると主張するため、両者は真っ向から対立します。このことを事前に十分理解し、双方歩み寄る姿勢が大切だと思われます。また、助成金や補助金の対象となる業務でもあるため、不正受給等が発覚するケースも見受けられます。そのため、企業調査ではこの辺りもしっかりと確認する必要があります。